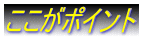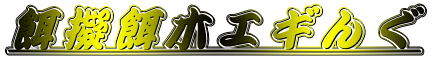
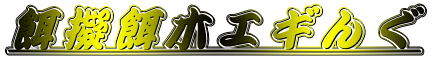

 |
愛着のでるエギキャリー |
餌木の発祥地は南西諸島とされている。島の漁師の餌木による舟曳漁法が長い間に九州、四国にそして本州にと北上し広まり、今では漁師のみならず、我々釣り人の中まで形を変え入り込んだわけである。材料として主に桐、朴の木が使用されているが、戦後の化学素材の発見から、現在は均一に大量生産出来るプラスチック製が幅を効かすようになった。各地の漁師方は現在でも自製の餌木を使用されている。
上写真 山陰型です。
一言でアオリイカ釣りといっても、活きアジ使用のウキ釣り、アジ泳がせのヤエン釣り、そしてエギングと釣り方はあります。アジを使用する釣り方は、活きアジの入手 が困難であること各地の漁港で一匹何某で予約販売をしている所もありますが・・・・その点、エギングの場合は手軽に行えると言う利点、テクニックさえ覚えれば、其れなりに可成りハマル釣りである。以下竿弘の一人合点
アオリイカを狙う場合、型は、兎も角、餌木による色は殆ど関係ないと思われます。漁師が使用する餌木は、オレンジに白色のツートンカラーしか使われません。其れで一晩に舟曳で三桁を捕獲されます。色は単なる釣り人の思いこみで、偶々釣れたときに使用したのがその色であって、他の色でも釣れたかもしれません。本人の使用して釣れた餌木の色。自己満足でしょう。色にこだわる人に、ゴメンナサイ
| 基本 | 茶・緑、赤・紫・オレンジ |
俗に一般的なヒットの色です。 |
| 定番 | 茶・紫 | |
| 昼 | 茶・オレンジ | |
| 夜 | 紫・赤 |
| 曳型 | シャクリ 軽 | シャクリ 並 |
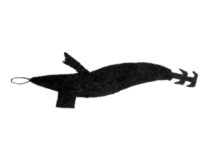 |
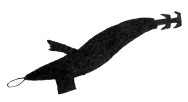 |
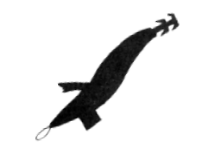 |
| 餌木に対して錘は軽め主に舟で曳く | アオリイカシーズン早めの小型アオリ用。錘の場所をチューニングすれば沈み方は自由になります。 | アオリ10月以降使用。錘の場所をチューニングすれば沈み方はもっと早く成ります。 |
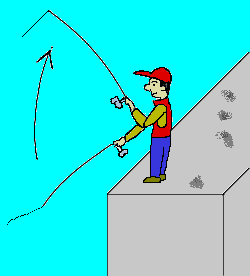 |
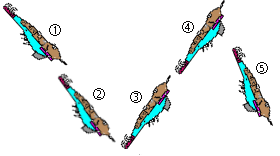 |
|
①で着水②底に向かって餌木は沈む |
|
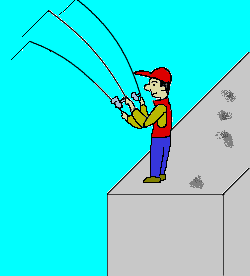 |
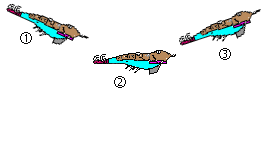 |
|
②で竿先をシャクル |
|
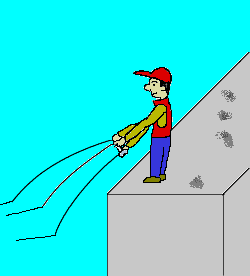 |
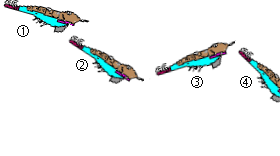 |
|
①~②に掛けて底まで落としす。糸ふけを取る。この時にアオリが居ると乗ってくる。 |
|
|
一度投げたところは、4~5回は打ち返して下さい。その時に釣れなくてもアオリは遠巻きにして餌木を追いかけていることが多いにあります。手前まで餌木を引っ張て来てあきらめずに餌木の後をよく見て下さい。アオリが着いてくるのが見えるときがあります。その時は餌木をチョン、チョンと動かして見ると、サッと餌木に乗ってくる場合があります。此も、俗に言う「見えイカ」です。 |
|
アオリイカの釣れる時間帯は、他の魚と違って夕闇成らぬ満月の夜と限られていましたが餌木ングに関しては、夜より昼間の方が良く釣れる。と言うより釣りやすいです。
なんと言っても、誰にでも簡単、手軽に出来ると言うことで、爆発的な人気に成った由縁である。
第一に自分の目でポイントが見える。
第二に餌木の着底後の糸ふけが確認。
第三にアオリが見える。
第四に活きアジ釣り師が少ない。
![]()
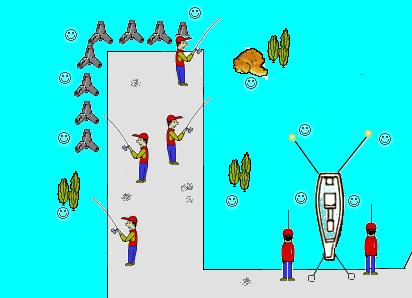 |
にこにこマークがポイントです。 |