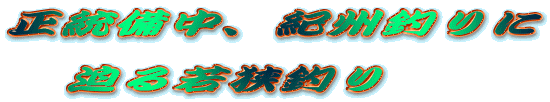

若狭釣りとは、正統備中釣りが改良された今様の呼び名である。備中釣りは1本のテグスを2本の竿で掛けたチヌを操る妙技である。勿論テグスは竿の2本分の長さがあると聞く1本にはテグス、1本には穂先に鈎(カギ)が着いている。その釣りの型は天下一品である。
今では殆ど行われてはいないようである。紀州釣りは、長竿リール付きで棒ウキを持って団子で釣る。若狭釣りはリール、長い竿が改良されて短く成り、戦後間もない頃、福井県三方地方、若狭本郷、京都府久美浜方面でカキ、真珠養殖筏などを利用し、それらに小舟を着けて(カセ)、釣りをさせ殆ど同時に発祥したようである。現在は廃船を、又、釣り専用にガッチリと材木で枠組みされ板・コンパネ等で作られ、最近は女性でもトイレに困らないようにトイレが設置されている。
他の黒鯛釣りと異なり基本的には攻撃的である。どんなに小さな当たりでも、初回で、正確かつ敏速に合わせ鈎(ハリ)に乗ったチヌは、その場から素早く離してやる。他のチヌが散らないようにすると言う点である。鈎のすぐ近くに付けた、錘がこの釣り型で黒鯛の当たりを、正確に捕らえる事が出来る。しかし現在の筏釣りは当たりがあれば、道糸を送り次の当たりを待つ保守的な釣り方に変わってきている。
チヌ釣りではないが、筏の周辺に生け簀網を張り巡らせ大型の魚を放流して釣らせる今流行の海上釣り堀がある。
鈎がチヌの口付近に掛かったのを・・釣った
鈎をチヌに呑まれたのを・・・・・・釣れた
団子釣り(以前は赤土にサナギ粉を混ぜた物を使用したが磯荒れ海底を荒らすため使用禁止となっている。)現在は雪花菜・ヌカサナギ粉がベースに成っている。団子にアケミ貝又はシラサエビ等を包んで足下から静かに海中に落とす。竿は短い物を使用。九対一の先調子、穂先十分の一位で、当たりが取れること。攻撃も待ちもできる。
筏竿(1.8㍍)予備竿 椅子(折りたたみ式) 鈎チヌ 3~4号 竿受け (筏用) クーラー ハリス1.5~3号 タイコリール(両軸筏用) スカリ(魚籠) 道糸2~3号 石突きロープ タモ (玉網) ナイフ(アケミ貝割り) 偏光グラス(サングラス×) 撒き餌シャク ハサミ 日よけ帽子 雨具 オモリ(大、中,小、等)
海には四季折々の釣りができます。波静かな所に設置され船酔いをする人にも歓迎され、筏も地方や設置場所に依って魚種がかわりますが、色々な魚が釣れます。ざっと数えて見ただけでもチヌ、グレ、スズキ、カレイ、サヨリ、カワハギ、メバル、ガシラ、キス、アオリイカ、、ヒラメと多様です。水深があり潮通しのいいとでは(舞鶴三浜)マダイ、石鯛が釣れるところもあります。チヌだけじゃないぞ。
場所・風・物量。三点で釣果は大きく左右される
釣り筏は大抵地元の漁師又は渡船屋、漁協組合が設置しています。釣行日より数日前に、余裕を持って連絡を取り予約をすればいいでしょう。連絡をする場合は遅くとも午後7時迄にはしたいものです。商売柄早朝の仕事のため夜は早くにお休みに成られます。当日の飛び込みでもやれないことはありませんが、やはり予約を入れておいた方が、渡船の時刻や釣況、そして、いま釣れている魚種、天候の具合を教えてもらえるので確実である。納竿時間も忘れずに伝えておくこと。
若狭湾近辺設置筏
天気予報などで台風の接近が知らされたとき釣行が微妙な場合があります。こんな時は電話一本を入れて確認してみること、商売上経験的にやれるやれないを早めに判断しますから、適切な返事を返してくれるはずです。風は、筏釣りでは微風ほどあっても釣りには、影響するから大敵です。向かい風は、なるべく避けなければ当たりは取りにくい。
アケミ貝が、基本であり餌取りの多い時は、土団子にして貝をくるむ。貝は、前以て幾分(1㎏、2㎏)か漬しておく事です。筏の上で漬すと、海底に音が伝わり黒鯛が散ってしまうからである。
丸貝を使用する時は、親指第一関節位のアメ色をした、貝を使うと良い。物量は、撒き餅のことてあり撒き餌を惜しんでいてはこの釣りは、出来ない。持参の餌は半分以上が 撒き餌用である。
釣り始めに半袋程一帯に広く撒いておく、後は、2~3回竿を上げる毎に、3~4個程 撒く操作を繰り返す。手返しをなるべくこまめに行うこと、日中は貝が弱るので、布バケツに貝を入れ度々海水を入れ替えて置けば良い。
納竿時に、貝が袋に残っているような状態あれば適切に撒き餌を、していない証拠であり気付けたい。
若狭釣り(備中)、鈎り近くに錘を仕掛け黒鯛が餌をくわえた瞬間の当たりを正確に取る。餌が底に着くか、着かないかの瞬間に当たりがわかるのも、この釣りの特徴である。
小さな当たりで1~2㌢大きな当たりで3~4㌢の確かな、節のある当たりが出る。当たりがあれば瞬間に竿を衝き上げるように大きく合あせる。黒鯛が掛かったら後は黒鯛の引きに合わせて、リールを巻いたり、戻したりの繰り返しで巻き捕る。
黒鯛を掛けたら最初は、強い引き込みがあり続いて二回程引き込む、後は、横か手前に走り出す。黒鯛が手元に来て、巻き取りにくい時は腕を突き出す要にしてやれば巻き取りやすい。筏の下へ引き込まれると、捕り込めないので注意の事。
ハリスの透明度は無視出来ないが、太い細いの差で潮流によつてハリスが受ける水圧、又は、魚の食いに大きく影響すると聞くが、平常の海水が少しでも濁っておれば、ハリスの号数など関係ないと思う。
澄み切った時などでもハリスは見えていると思うのに魚が釣れるのは団子を水中に落とすと同じに、団子はゆっくりと溶けつつ海底に落ちてゆく、その時の濁りがハリスを隠してくれ、撒き餌の効果もあり魚はハリスそのものより餌に食いついてくれる。
3号のハリスでも良く釣れる事がある。ハリスの号数は余り神経質に考える必要はなさそう。
竿の長さ 1.5m~2.10m 予備竿必要 ハリス 竿の半分位にする事。ハリスが長ければ黒鯛が掛かった時に玉網ですくいにくく、ヨリモモドシが竿先のガイドに当たり穂先を折ってしまう。
錘 鈎の上、5~10㌢位。水深や潮流、餌などで 使い分ける。
石突き 竿の石突きには置き竿をしても魚に竿を持って行かれないように伸縮するウレタン製のスプリング状の物をを付けて置く事。
ムキ身 貝を取り出して身の堅い所から柔らかい所に鈎先が行くよう。
半貝 貝の片側を取り身の堅い所から柔らかい所へ鈎先が行くよう。
蝶々 ナイフで貝を割り身の堅い所から柔らか い所を通し堅い所へ鈎先が行くよう。
丸貝 アメ色をした貝を全部開かぬように爪楊枝で刺し鈎先が外向きに成るよ鈎を中に入れる。
TOPぺーじ