新出漢字の学習は、単元の学習と切り離して進めるということが基本です。その理由は、漢字はくり返して練習することが習熟には絶対必要なことで、もし単元通りに学習をしていくと、学期末の漢字を復習する時間がなくなってしまうからです。私はあえて新出漢字の指導はできる限り早く行い、その分反復の回数を増やすという方法とるようになっています。
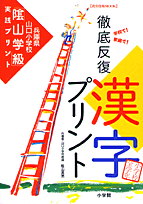
新出漢字を、学習する方法はいくつも提案されています。いずれの方法にも優れた点があり、自分がやりやすい方法で進めればいいでしょう。しかし、私は2週間で新出漢字の指導を終えるということを提唱しました。そして、そのための教材として、徹底反復漢字プリントを出しました。これはまず、1年間に覚える新出漢字の混じった例文を何度も読み、だいたいを頭に入れ、そしてその後、その例文の問題をコピ−して何度も繰り返して練習するというものです。7回も反復練習をすると、だいたい子どもは覚えて、書けるようになるものです。
下はさっそく使ったお母さんの言葉です。
| 6月25日付け掲示板より 徹底反復漢字プリントに同じ例文を7回繰り返すとありましたが本当に7回繰り返すと習得できるようです。フォーラムAの漢字リピートプリントで同じようにまとめ読みから始めて総復習を6回くらいコピーしたのをするとその学年分は書けるようになりました。 なかなか書けない漢字も10も20もずらっと書かせることなくただまとめ読みと総復習の繰り返しで書けるようになるからえらいもんだなと思います。きっと例文を読むごとに漢字もおなじみのものになるんでしょうね。 なによりも私が良かったなと思うことは息子が例文をすらすらと読めるようになってくるにつれて 「そろそろこの漢字は書けるかも。」とわかるようになってきたことです。 漢字の習得はただひたすら手を動かして書き続けないと覚えられないと思っていたけど例文をすらすら読めるようになると書くこともスムーズにいくようです。 せっかくたくさん漢字を書いたのにちっとも覚えられなかったらがっかりですもんね。(以前はそうでした。)漢字を覚えると使ってみたくなるようで息子の描いているマンガのせりふのところも漢字が増えていました。 「ぶき」→「ぶ器」(武器のことです)とか。 がんばって5年生の漢字やったら「武器」と全部漢字でかけるね。 |
完全な習熟のために大切なのは、新出漢字の学習を遅くとも7月中に終わることです。それは、夏休みの宿題に漢字の総復習をするためです。漢字の総復習では、漢字リピ−トプリントがいいです。50の短文の中に、一学年分の漢字がすべて入っていて、それもテスト形式になっていますから取り組みやすいものです。
夏までに一応新出漢字が覚えられたとすると、今度は漢字を覚えるのではなく、直接すべての熟語を覚えさせるということをします。それはとてつもなく多いので無理だとかつては考えていました。しかし、小学校で覚える漢字の数は約千。平均して漢字1字について熟語の数が平均5個として小学校で覚える熟語は五千。しかし熟語は2字の組み合わせですから、実質的には半分の二千五百。そのうち3割は自然に覚えるとすれば平均的な子で熟語は千数百覚えればよいのです。この千数百を4年生から学習すれば、1年に約五百、一日2つでいいのです。継続は力なりといわれますが、毎日こつこつすることはこれほどに不可能と思えることを可能にしてくれるのです。そこで熟語プリントが徹底反復漢字プリントの中に入っています。そして、これを秋にある程度練習させ、何度も練習しましょう。
なぜ熟語を練習するかというと、子どもはその漢字が、教科書にある熟語などでは書けても、その漢字が別の熟語で使われていると書けなくなるからです。特に4年生以上になると、熟語の数が増えるので、その傾向は強くなってきます。熟語に習熟するということは子どもの語彙が増えるということなのです。