�^�[�Q�b�g�̏Љ�z �X�Y�L
�u�t�B�b�V���C�[�^�[�i���H���j�v
�o�����@�Z�C�S���n�l���X�Y�L�@�n���ɂ���ĈقȂ�܂��B
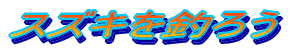
���ߘp���ӂł���ނ�ŁA�e�Ղɒނ�鋛�u�Z�C�S�v�B�X�Y�L�͑召��킸�u�V�[�o�X�v�Ƃ����Ăі��ŁA�����ߔN��҂̊ԂŃ��A�[�ނ肪��l�C�B����͐����a�ł̒ނ�����Љ�����܂��B���̋��́A��������ɂ��������Ăі����ς��u�o�����v�B���悻40�����܂ł̂��̂��u�Z�C�S�v�A40�`60�����܂ł��u�n�l�v�A����ȏ�̂��̂��u�X�Y�L�v�ƌĂ�Ă��܂��B�H���͋ɂ߂Ăǂ��ҁB�A�W�A�C���V�A�R�m�V���A�n�[�ȂǓ��p�ɏZ�ޏ����𒆐S�ɁA�G�r�Ȃǂ̍b�k�ނ�S�J�C�Ȃǂ̊��ނ��ߐH���Ă���A3�����̓C�T�U��ǂ������Ęp���ɓ���A���Ă̍��ɂ͏�����ǂ��Đ��k�サ�Ă���قǂł��B���̒ނ�ł́A�`�k�A���o���A�A�u�����ȂǁA���܂��܂ȊO�����ނ�Ă��邱�Ƃ��y���݂̈�ł��B
�ފ��͎��3���`6���i�������㏸����t��j�ƁA11���`12���i�������}���ɒቺ����ӏH�j���x�X�g�V�[�Y���B���ɔӏH�́u�����v�ƌĂ��A��^�̂��̂�ނ�グ���D�̃`�����X�ł��B�X�Y�L�̓G���̕������J�~�\���̗l�ɉs�����߁A�ނ�Ă���������ƐG��Ȃ��悤�ɒ��ӁB�܂��A�w�r����K�r�����Ƃ����Ă���̂ŋC�����邱�Ƃł��B�K���^�I�����Ŋ����l�ɂ��Ă���߂܂��ĉ������B�X�Y�L�̖��́A�召�W�Ȃ��A�N�Z���Ȃ���i�Ȕ��g�������ŁA�{�̉ď�ɂ́u�v�������߂ł��B���������ɂ͂����g������Ԃ���ԂŐH�������܂��ō��B����ȊO�ɂ̓z�C���āA���Ă��A�t���C�Ȃǂ������ł��B
��h�����Z�C�S��_���ɂ́A���A�[�ނ��d�C�E�L�ނ�Ȃǂ��������܂��B���ł̓V���T�G�r���T���Ȃ���ނ�u�G�r�T���ނ�v���ł�����ŁA�l�C�̍����ޖ@�ł��B�ł����̒ނ���ɂ͉a�オ������܂��B����͐��ނ���F����ɏЉ�Ă݂����Ǝv���܂��B�܂��啨��ނ������Ƃ��Ȃ��Ƃ����r�M�i�[�̊F����A����A�C�̃t�@�C�^�[�u�Z�C�S�E�n�l�v���q�b�g�����A���̘r�����тꂳ���Ă��������B
����̊m�F
�^�i�i�E�L���j��ݒ肷�邽�߁A�E�L�~�ߎ����ړ������܂��B�Z�C�S�ނ�̃^�i��1.5�`2�q�����x�ɐݒ肷�邱�Ƃ������悤�ł����A���ꂼ��̃|�C���g�ɂ���ĉ���ς��܂��B���n���͂̒ނ�l�̏����Q�l�ɂ���Ƃ悢�ł��傤�B
4.5�`5.4m�̈�Ɓi�`�k�ƂŌ��\�j�Ƃ̒����ɂ��ẮA4.5������Ƃ��đI�ԂƂ悢�ł��傤�B�܂��A�C�ʂ܂ō���������|�C���g��e�g���|�b�g���肩��Ƃ��o���ꍇ�ɂ́A���߂�5.4�����g���Ղ��Ǝv���܂��B�Z�C�S�̈����͋���ł����A�Ƃ̑����͂������1�`1.5�����x�̂��̂őΉ��ł��܂��B���S�҂̕��ɂ�5000�`8000�~�O����x�̂��̂ŏ[���B���Ȃ݂ɊƂ̍����ɂ��Ă͐����������Ă����قǕ�悪�����Ȃ��Ă����A�啨�ɂ��ς�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�܂��A��ނ�ɂ́A�C���^�[���C�����b�h�͕��ւ̎����݂����Ȃ��̂ł����߂ƌ����܂����A���������Ȃ̂���_�B1.5���~�ʂ���̔�����Ă���悤�ł��B
| ���^�X�s�j���O���[�� | 3�`4������100���O�㊪������́B |
| �_�E�L | �����ȃA�^�����������E���Ă���銴�x�̗ǂ����̂��g�p���邱�ƁB�Â����ԑт���Ƃ��o���ꍇ������܂��̂ŁA�E�L�̃g�b�v�ɃP�~�z�^�����Z�b�g�ł�����̂�A�d�C�E�L�Ȃǂ��������Ă����K�v������܂��B�����̏ꍇ�͐����S2�`3���^�C�v |
| �X�i�b�v�T���J�� | �V���E�L�d�|������邽�߂̘A������B�_�E�L�̑��i�ǁj�����Ɏ��t���܂��B |
| �b | �G�T�̐���[�|���ɂ��邽�߂Ƀ`�k�b5�`6���E�Z�C�S�b15�`17�����g�p���܂��B |
| �n���X | 2�`3�����Q�B��q |
| �I���� | �I�����ɂ��ẮA�E�L�̕��͂ɔ�Ⴕ�܂��B�����E�L�̏ꍇ�́A���c�u�V����g�p�B�����E�L�ȊO�̓E�L�ɍ��������B�N�b�V�����S�����t���Ă���A�n���X��ɂ��o���V�̊m�����Ⴍ�Ȃ�܂��B |
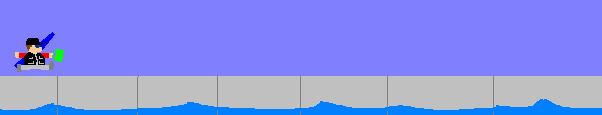
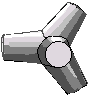




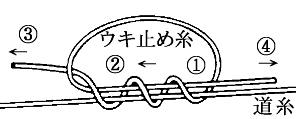 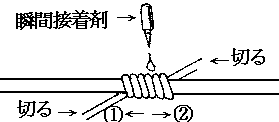 |
�E�L�~�� |
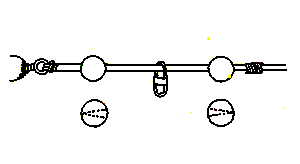 |
�V�����ʁE�V�����E�L �V���E�L���E�L�~�ߎ������ɒ�~�����邽�߂Ɏg�p�B���̏��������X�`���T�C�Y���悢�ł��傤�B �@�E�L�~�߃Z���ʂ́A�E�L�~�ߎ��̕����ցA�ׂ�������ʂ��B �A�T���J���i�X�i�b�v�j�����A����������ʂ��B �B�Ō�ɁA�������h�V�����ԁB |
�E�L�~��
��
�@
�A
�B
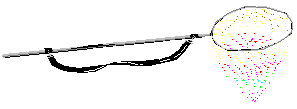 |
|
�ʃA�~�i�^���j |
 |
|
�G�T�� |
���̗l�ɂȂ�Ȃ��悤�ɋC��t���܂��傤
��
3���Ԓ��x�̒ނ�ł����500�~�قǁA����ȏ�̎��Ԃł�1000�~���x�̐����K�v�ƂȂ�܂��B��y��������̔g�~�ނ�ł����A���d�˂�ƃG�T�オ�������܂��B�G�T���c��ΊC���Ő���̑����ɂ���Ηǂ��B�^�I���Ŗؔ�������ݐV�����������ė①�ɂɓ���Ă�����2�`3���͎����܂��B
���̑�
�N�[���[�E�X�g�����K�[�E�^�I���E�n�T�~�E�v���C���[�E�o���h�G�C�h�E���ʼnt���Ȃǂ��K�v�ł��B�܂��A�Â����ԑт���ނ�ꍇ�́A�w�b�h���C�g������d���Ȃǂ����Q���鎖�B
�y�d�|���̏����z�@�܂��͎���Ŏd�|�����Z�b�g�B
�P�D�ƂɃ��[�����Z�b�g���A�K�C�h�ɓ�����ʂ�
�X�s�j���O���[�����Ƃ̃��[���V�[�g�ɌŒ肵�܂��B���[���̃x�C���������������A��O�̃K�C�h��菇�ɁA�����������点�Ă����܂��B
�Q�D�E�L�~�ߎ����ɃZ�b�g�@�E�L�~�ߐ}�Q�l�B
�E�L�~�ߎ��ɂ́A�ݒ肵���^�i�ŃE�L���~�߂�Ƃ����A�d�v�Ȗ���������܂��B��������ۂɂ̓E�L�~�ߎ��̗��[�������������邱�ƁB�E�L�~�߂ƂȂ�R�u�i���іځj���ł����ꍇ�ł��A��������ړ����������ɃX�J�X�J�ł͑ʖڂƂ������Ƃł��B��������ƒ��ߍ��܂Ȃ��ƁA�ݒ肵���^�i�i�E�L���j������Ă���̂ł����ӂ��B
�R�D�V�����ʁi�V�����E�L�j���ɃZ�b�g�@�E�L�~�ߐ}�Q�l�B
�V�����ʂɂ́A�V���E�L�d�|�����Z�b�g�����ł̏d�v�Ȗ���������܂��B�V���E�L�d�|���́A�E�L�~�ߎ��̎��ɃV�����ʂ�ʂ��A���̎��ɃX�i�b �v�T���J����ʂ��܂��B�������A�E�L�~�ߎ��̎��ɂ����Ȃ�X�i�b�v�T���J����ʂ��ƁA�X�i�b�v�T���J�@�@���̌��������ȃE�L�~�ߎ��̃R�u��ʉ߂��Ă��܂��A�ݒ肵���^�i�ŃE�L���X�g�b�v�@�@���܂���B�܂�A�V�����ʂ̓X�i�b�v�T���J���̃X�g�b�p�[�I�Ȗ���������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�܂��A�V�����ʂ��g������ɃX�i�b�v�T���J���̌����y���`�ŋ��߂ăE�L�~�ߎ������Ŏ~�߂�Ƃ������@������܂��B
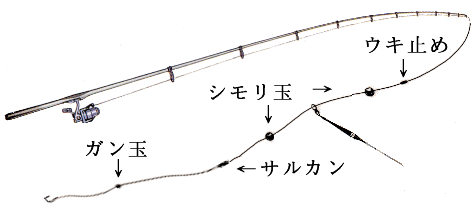 |
|
�S�D�X�i�b�v�T���J�����Z�b�g�@�E�L�~�ߐ}�Q�l |
 |
����ɂđS�ăZ�b�g�B�ނ��Ɍ������܂��B�E�L�͂Q���A���͂Q�������@���ăE�L�ɕ������ăe�[�v�Ŋ����t�������E�L�ɂ��Ă��艓���������܂��B |
���ނ���Ă���Ȓނ��
�ނ��ւƓ���������A�܂��͂��̓��̒ނ�������߂܂��B�Z�C�S�ނ�ł́A�͌��̎̂ĐΎ���A�C�ݐ��̉��̋삯�オ��Ȃǂ��|�C���g�ƂȂ�܂��B
��ނ�̏ꍇ�́A���Ԃɐ��A�l�ӂ̋삯�オ�蕔���������Ă��Ă��A��ނ�́A�����x������܂���B�Ƃ��o���O�ɂ͕K�����邢���ɐ��A�C������Ă����܂��傤�B�̂Đ߂��ɂ͑��G�r�A�������Z���ɂ��Ă��܂��B��ɂȂ�Ə������̓������݂��Ȃ�A�Z�C�S�̊i�D�̃G�T��ɐ��邩��ł��B�|�C���g�̐��[�ɂ��˂��܂��������������ꏊ�ł�1�q����i��1���j�܂łɕ�������ݒ肢�����܂��B
���ɁA�O��̐����̒ʂ�A�Ƃ�L���Ďd�|�����Z�b�g���܂��B�����āA���𐔖{�[�|���Ɋb�Ɏh���܂��B
���Ɏd�|���𓊓��B�|�C���g�́A�̂Đ̒���܂�|�C���g����⒪��B�U�荞��A���ɏ悹�Ă������ƃE�L�𗬂��Ă����܂��B�d�v�ȃe�N�j�b�N�̈�Ƃ��āu�U���v������܂��B�P�Ƀ_���_���ƃE�L�𗬂��Ă����̂ł͂Ȃ��A���ܓ������ėU���������铮���������邱�Ƃ��A�m���Ȓމʂނ��ƂɂȂ�̂ł��B
���̗��ꂪ�قƂ�ǖ����ꍇ�ɂ́A�d�|������������������Ȃ�������点�ėU���悤�ɂ��܂��B�A�^�����o�n�߂�悤�ɂȂ�܂��B�i�������A�����ɂ��A�^�����o�Ȃ��ꍇ������܂��j��ʓI�ȃZ�C�S�̃A�^���́A�E�L�̃g�b�v���u�c���c���v�Ɖ��������܂ꂽ��Ɂu�X�[�b�v�ƃE�L���������܂�Ă����܂��B�����������A�����̗ǂ��ꍇ�ɂ́u�X�p�b�v�ƈ�C�ɃE�L���������݊Ɛ�܂ŗ��邱�Ƃ�����܂��B
����Ƃ͔��ɁA�����̒Ⴂ�����Ȃǂ͐H�����a���A�u�c���v�ƃE�L�̃g�b�v���P�E�Q�߁A���������܂����x�̃A�^�������o�Ȃ��Ƃ��́A���̂悤�ȏꍇ�ɂ́A�U����������v�̂ŏ��������Ă��ƁA�E�L���������܂�邱�Ƃ�����܂��B
�A�^���������Ă����A���Z�͋֕��B�E�L������ł���4�`5�b��ɃA���Z������悤�ɂ��܂��傤�B���Ɋ��������ɂ̓A�^�����������A�H����������₷���̂ł����ӂ��B
�Z�C�S�̈����͋���ł��B���S�҂̕��ɂ́A���̈����ɂ�����������Ă��܂����Ƃł��傤�B�T�O����������̂ɂȂ�ƁA�E�֍��ւƖҗ�Ɏ������܂��B�Z�C�S�n�l���|�������ꍇ�ɂ͂Ƃ����ɊƂ𗧂ĂāA���߂��������i�Ƃ̔����͂𗘗p���ċ�����点��B�K�v�ȏ�ɉj�������Ƃ́A�n���X��̌����ɂȂ�܂��B����ŁA�n���X�����ƌ������A�Z�C�S�̎��̓T�E���h�y�[�p�[��ɂȂ��Ă��邽�߃n���X��A���́A���Ȃ�U���U���ɐ���܂��B�n���X��1�{�ނ�グ�閈�Ɏ��ւ��邱�Ƃ��������ߒv���܂��B�j�Ȃ����O�ւƊĂ���悤�ɂ��܂��B����ƌo����ςނ��Ƃɂ���Ď���ɏ�B����悤�ɂȂ�܂��̂ł����S���B
�g�~�ۂ��X���b�g�ɂȂ�������A�e�g���Ȃǂ�����|�C���g�ł́A�����̏�Q���ɐ��肱�܂�Ȃ��悤�ɒ��ӂ��邱�ƁB�Ȃ��A�b�|���肵���Z�C�S�̓G���i���ʂł̃W�����v�j�����邱�Ƃ�����܂��̂ŁA���̍ۂɂ͓������ɂ߂Ă͂����܂���B
�|�������Z�C�S��߂荞�ނ��߂ɋʖԁi�^���j�͕K�g�B�C�ʂ܂ō����ނ������邽�߁A�T���O��̂��̂����Q����悤�ɂ��܂��傤�B�^������i�����|�������ꍇ�̕߂荞�݁j�́A�|���������𑫌��܂ŊA�K�����̓������荞�ނ悤�ɂ��܂��B
�u���܂��߁v�܂��́u�[�܂��߁v�̎��ԑт�_���悤�ɂ��܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�務�����F�肵�܂��B�ƍO�@
�@
| ����Ŏd�|���ނ̏����������A�ނ��ւƏo�|���܂��傤�B |
|
����ł͂��̋@��ɁA���₭�ނ��ŊƂ��o������@�����������܂��傤�B��قǂ�1�`4�ɂ�����v���Z�X�ŃZ�b�g�����d�|���́A�������h�V�̂�����܂ł��炵����ԂŃ��[���������グ�A�K�C�h�J�o�[����ɃZ�b�g���܂��B���̃X�^�C���Œނ��ւƎ��Q���A���Ƃ̓n���X�Ɩ_�E�L���Z�b�g����A�����ɒނ���n�߂邱�Ƃ��ł���Ƃ����킯�ł��B��قlj�������d�|���̏�����ނ��ōs�����Ƃ���ƁA�����Ȏ��Ԃ��₵�Ă��܂����ƂɂȂ�A���������̍D�����������Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B�ނ��ł͋ɗ͖��ʂȎ��Ԃ��Ȃ��A�����悭�Ƃ��o���悤�ɐS�����������̂ł��B���Ȃ݂ɏ����A�ނ�ɍs���ꍇ�́A���b�h�x���g�ł܂Ƃ߂��^���ƊƂ��E���ɁA�����č���ɂ̓G�T���E�N�[���[���A�w���ɂ͏����ނȂǂ���ꂽ�i�b�v�T�b�N��w�����ލs���Ă��܂��B�����܂ł̏����̓I�[�P�[�ł����H�d�|���̏����������Ύ��Q���铹����m�F���āA�ނ��ւƃ��b�c�S�[�I |
|
�y�ނ��ł̊Əo�������z�Ƃ�L�� |
|
�_�E�L���Z�b�g |
|
�n���X�����̎d�|�����Z�b�g |
|
�E�L�~�ߎ����ړ������� |