 自然と遊ぶ
自然と遊ぶ  自然と遊ぶ
自然と遊ぶ
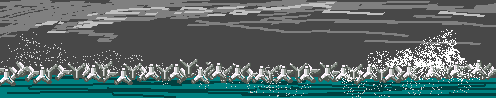
地球の三分の二を海が占めています。我々とは切っても切れない水との関係、 約40億年前に海中で生命が誕生して以来、海には様々な生物がすみ、進化を続けてきました。
時を後にして地質時代、約2000万年前に、この日本が大陸続きの時、今の日本海の一部が、陥没したところに湖が出来上がり、氷河が溶け浸食が始まり東シナ海から黒潮が流れ込み対馬海峡を作り日本海ができました。
約100万年前に舞鶴湾ができその頃に青葉山が噴火したと言われ、そして約1万年前に舞鶴人が出現し、縄文時代には大浦半島周辺の潟に暮らしが始まりました。東の大浦半島一帯と西の金ケ崎、白杉、青井一帯に、凡海郷(オオシアマ)の大地が在りました。そして三浜、小橋,野原、の三村が本拠地としていたらしく、古墳も沢山出土しています。この凡海郷は古墳時代に沈没したと言われます。又、この浦入で、平成10年に 考古学者が、よだれを垂らし泣いて喜ぶ、日本最古の丸木船が出土致しました。この地方は舞鶴でも由良川共に最も古墳の多い所です。火力発電所の工事もそのたびに、中止して発掘調査が行われているようです。
この火力発電所が建設されている入り江(浦入湾)が、 腕のようにのびた陸地がありましたが、今は見る影もなくこの場所が「元橋立」であり千歳の手前の突き出たところが文珠である。
神世の昔、夜更けに神様が浦入に天橋立を造っている時に、対岸の白杉に住む老婆が夜中に、目を覚ましてガサガサと、音を立てたためにニワトリが鳴いて、朝が来たと思った神様は、造りかけのまま天に帰ってしまい、後日に宮津の地に今の天橋立を造ったと言われています。
日本近海には、全世界の海の20%の魚が住んでいます。若狭湾は、全国的に魚の宝庫であり、漁港も多くその為に防波堤も多い、休日にもなると京阪神からの魚を求め、釣り人も多くにぎやかである。この舞鶴湾に生息している魚類は、最低でも約90種類、その内、我々が釣りの対象にしているのは、ほんの数種類にすぎません。舞鶴市も西は神崎、東は水ヶ浦この間、海岸線は約100キロ以上しかし本当に竿をだせる所はほんの僅かである。その僅かな所でこれから釣りを行おうと言う方に、釣りの面白さ、楽しさ、奥の深い遊び、人類最古の遊び。嵌れば抜けきれない世界です。老婆心ながらお話をしたいとおもいます。何分、完全無欠のものではありません。非難される部分多々ありますが、楽しみの助言となれば幸いです。
海は、いったい誰のものか。
海に関心があるものなら、漁業者ならずとも、我々釣り人がこの疑問を一番に抱きます。土地や物のには、所有権があります。其れでは、「海は誰かの所有物か」という法律上の性質については、最高裁判決で、「海は土地ではなく、所有権の対象にはならない」として、それまでの論争に終止符をうつ明快な判決が出ています。内容は「海は、古来より自然の状態のままで一般公衆の共同使用に供されてきたところのいわゆる公共用物であって、国の直接の公法的支配管理に服し、特定人による排他的支配の許されないもの」と判示されました。つまり、海は、誰の所有物にもあたらない「公共用物」というものです。
ところが、昨今、海岸を歩いていると、その地域の漁業協同組合名で漁港域への立ち入りや関係海面への入域を規制している立て看板を目にする事が多くなっています。さらに、遊漁の釣りやダイビング、ジェツトスキーなどマリンレジャーを楽しもうとする人たちが、地元の漁協が管理する漁業権水域や周辺海域に入域して海を利用する場合には、漁業協同組合や漁村の関係地区団体の了解を得たり、一定の料金を支払ったり、漁場の区域に入域規制水域が設けられていたりします。
海は「誰のものでもない」という最高裁の判例があるにもかかわらず、国民の誰もが自由に水域を選んで、釣りをしたり、ダイビングをすることが、なぜできないのかという新たな疑問がわいてくるのも不思議ではありません。海を利用する我々にも問題があるのです。地元漁業者とのあいだで、いろいろなトラブルが全国各地で起きています。生活の糧にしている人、楽しみの糧にしいる人との違いです。
漁業者が海を「われわれの海」と呼ぶ。その中で漁港と言われる場所で、釣りを楽しみ一日を過ごす。さてその後の清掃は誰が・・・・。「われわれの海」と言われても仕方がない。
![]()
出発前の注意事項
気象情報に注意をして最新の情報で釣り場の天候を予測し荒天が予想されたときは思い切って出発を中止する勇気が必要です。時間にも心にも余裕を持ち充分に計画を立ててお楽しみ下さい。海は古女房と同じで結婚生活が長いと、旦那は女房の全てを知っているとおもっているが、実は上面だけで何にも知っていないわけ、海も全く同じで奥が深い物で、御機嫌次第でとんでもない暴れ方をする。要するに、海も女房も軽く見ては大怪我をすると言うこと。
単独行動は避ける。複数で釣りをする事、年齢・体力の合った人を選び釣りを楽しむのがコツである。万一のアクシデントにも一人では対応できない場合が多いにあります。
体調はベストに。充分な睡眠と万全な体調て出かけること。釣り場で体調を、悪くすると救急活動に時間がかかり又釣り仲間に迷惑がかかります。
行動予定行き先を必ず家族又は友達等に伝えてから出発する事。
服装についても軽くて動きやすく水や風を通さない、赤や黄色等の目立つ服装でお互いが確認して、又救命胴衣を着用の事。靴は底に凹凸のある物。裏底のツルツルは絶対に避けてください。
救命胴衣で助かると言うより、海に落ちないようにする事が一番である。救命胴衣があるからと言う安心は禁物である。釣り釣り場では間違ってもふざけたり、冗談は避けたいものです。
![]()
危険な所はさける
毎年ゴールデンウイークや、夏休みなど家族連れの、釣りは微笑ましいが、思わぬ所に落とし穴がある。子供は魚が釣れなければ、遊びだし親は竿先を見るのについ夢中になり、その間、子供は防波堤の、端から端まで走り回り、挙げ句の果て消波提ブロック(テトラポット商品名)の上へと、消波ブロックは設置されても2~3年は海底の砂の動きでゴトゴトと音を立て、動くことがある。ましてや、滑って、落ちれば怪我では済まない。大人でもまず助かることは皆無である。お天気の時でも岩場で一部濡れているところは必ずと言って良いほど波もしくは飛沫がかかるので、側には寄らないことが肝心である。しかし、この様に、釣りのルールを守れば、女性、子供達、そしてお年寄りでも安全にお魚さんと、楽しめるはずである。
一時間幸せになりたかったら、酒を飲みなさい。
三日間幸せになりたかったら、結婚しなさい。
八日間幸せになりたかったら、豚を殺して食べななさい。
永遠に幸せになりたかったら、釣りを覚えなさい。
中国古諺
釣り人の代名詞
ゴルフにしろ、スキーにしてもインストラクターと言われる指導者がおられるが、釣りに関してはインストラクターなる人物は非常に少ないのです。かの有名な太公望、この人のプロフイールは、兎にも角にも、ある日、揚子江の支流の渭水で世間から、離れて釣り糸をたれていたが何日も魚は釣れなかった、そこへ一人の旅人が通りかかり、お節介にあれこれと釣りの手ほどきをしたわけです。其れからと言うものは魚が面白いほど釣れたわけ、それをたまたま近くの村人が見て、何と良く魚を釣る人と、村に帰り渭水には、釣りの名人が、いると広がったわけ?。 この太公望ですら、釣りのインストラクター、師匠がいたわけです。しかし、魚が良く釣れると言っても、「魚も資源」有限であることを忘れずに、釣れると言ってムヤミヤタラに釣らずに、次の釣行に楽しみを残して置きたいものである。
最初が一番大事
何事に置いても、最初が一番大事なことです。思い浮かべて下さい。ゴルフの例え、私は、クラブを握ったことはありませんが、グリーンに乗せるまでの、第一打いろんな人にいろんな角度で、教えを受けたはずです。釣りに置いても、春夏秋冬、四季に応じて釣る魚、又、その仕掛けは、それぞれが異なる訳です。よく何でもいいから釣れたらよいと、言われる人がいますが、お魚さんに大変失礼です。目的を持った釣りをしたいものです。
環境
釣りをするには、地形、そして海底を知りなおも魚の習性を知り四季を釣りたいものです。この様に、お話をすると、地形はともかく海底はと、よく言われます。人間が自然を破壊するまでは、山肌の延長に、谷があり、川があり、平地がそして海がありました。海岸線で岩やゴロ石があるところは、海の中もある程度そのような状態になっています。一番良くわかるのは砂浜です、陸地が砂浜なら海底も砂地です。
これが自然です、 地球上に存在する水のうち98%が海水で、2%が陸上にあるわけです。その水の97%が氷で3%が淡水です 。この水が無ければ地球上の生き物は、生きては行けないのです。自然は山から、環境破壊も山からと言うことで、植林をしなければいけない訳で、山から流れ出す水は、川に大量のミネラルを放出し、其れがやがては、海に、そうする事で少しでも、その湾が若返りするのではと言うことです。植林も杉や檜ばかりでは雨が降ればそのまま川に流れこみます。落葉樹を植えることで葉は落ちて土壌を作り水を蓄え、そして木漏れ日が差込まなくては自然に優しくないのです。山肌が死んでしまいます。
川もそうです、護岸、河川工事も結構だが川には、淵そして瀬がなければ水は浄化はしない訳です。淵は、水質汚れを沈殿させ、瀬は、水の中に酸素をとりいれる。ダムで言えば貯水池が淵であり、曝水口が瀬である。長年自然界に培われた海岸線、今や至る所に防波堤。防波堤が設置されれば、潮の流れが変わりその場所は良くても数キロ、数十キロ離れたところに影響が出てくる。此も考えなくては行けない。自然の中、空気中には-イオンが大量あり、この-イオンは人間に取っては大変必要なのです。森林浴の山、海水浴やこれから、お話をしてゆく釣り海には、-イオンが大量あるわけで、野山、海、自然にとけ込むのは、心身共にリフレッシュするわけです。川に聴き、海に聴き、魚に聴く、すべてバランスよく、その物の顔色を見ればその町の健康状態がわかる訳です。この後の話は、環境問題に取り組んでおられる方にお任せして話を戻します。 イオンとは、ラテン語で「夢のある未来」「永遠」という意味。
岩場、砂地に住んでいる、魚はそれぞれ種類が違います。仕掛けも当然変わります。
岩場は、浮き釣り
砂場は、投げ釣りと、なる訳です。
春
春の海の中は陸地より、1ヶ月以上も春の訪れは遅く、水温なども10度前以下で、特に冷え込みがひどく、雪が多く降った年などは、それだけ海の中の春は遅くなるわけで、魚の種類によっては水温が低くなると、目の緑に白い膜(油脂被膜)ができて冬眠状態に入り餌が見えず、食欲が出ないために釣れないのである。この頃に藻魚の類で一年で一番水温の低いときに産卵をする。他の魚の動きが鈍く自分たちの子孫を遺す弱い種類の手段である。浮き釣りで、生きエビや、オキアミで、海草やゴロタ石、岩の間を探ればメバル・アイナメ・ガシラ等のような根魚が釣れる。このオキアミはエビの形をしているが、南極で鯨などの餌になるれっきとした、プランクトンである。釣りの餌などに使用されだしたのは今から24~25年位前である。5月のゴールデン・ウイークが終わった頃から水温も日々に上がり、14~15度位になり、いよいよ釣り本番となる。砂浜では、この頃から投げ釣りでキス、小鯛、コチ等が釣れる。餌は青イソメ、石ゴカイなどを使用する。
夏
梅雨に入った頃から、俄かに釣れだす魚の種類が多くなる。防波堤そして身近な磯でグレ、チヌなどが釣れだす、荒磯の王者と言われる石鯛、いかに王者と言えども稚魚のときは縞鯛、又は、三番叟と呼ばれる時期には防波堤とか消波提などに居着く、釣師が一度は憧れる筆頭が№1がチヌであるでる。
チヌの和名は黒鯛
チヌ、すなわち黒鯛、真鯛が赤色に対して、薄黒い色であるから黒鯛と言う何故チヌなのか、昔、大阪湾を、和泉灘と言っていたが、さらに昔、神武天皇の兄・五瀬命(いつせのみこと)が奈良県生駒の豪族である長髄彦(ながすねひこ)との戦いで負傷したとき、手についた血を洗った海と言うことで、その辺りを血沼の海、それがなまり茅渟海(ちぬうみ)と言い、その茅渟海で多く漁獲されたので茅渟(チヌ)の名が出たという、和歌山から関東にかけ20cm内外の大ききをカイズ、カエズと呼ばれる、これは三重県の海津付近で昔、多く漁獲されたからこの名が出たと言われる。
チヌ釣りは難しいと言われるが、それほどでもない、昔は100匹のチヌを10人が追いかけていたが、今は100人が10匹を追いかけているから、なかなか釣れないのである。15~20㎝位の、チヌであれば場所によって数が望める所はある。
釣りやすく又、釣りにくい魚はグレ、(舞鶴近辺でツカヤ)この魚は撒き餌をして、水面近くまで浮かして釣るのですが、この時にただ撒き餌近くを、ウロウロしているときは全くといっていいほど釣れません。撒き餌をしたときに、上下運動しなければ駄目な訳です。つまり高気圧の時は水面が下がり、低気圧の時は水面が下がる、それぞれ魚にかかる圧力で食が異なる訳です。魚の視野は上空では光の屈折で約96°~160°の広範囲がみえる。前方は30°位でこれが一般に言われている、見える魚は釣れないと言うことです。ではどの様にすればよいのか、それは、自分から魚を、遠避ければよいわけ、つまり遠くに撒き餌をしてやる事により、自分から、魚を遠避けるのである。そしてその撒き餌の中にさしえを打ち込めば釣れるわけである。
河口などに、イサザ、稚アユが蘇上する頃、それらを追ってスズキが湾内に入りだしてスズキ釣りが始まる。梅雨入りから初夏にかけて一番良く釣れる、生エビを撒きながら、夜明け日没時を狙えば、おもしろい。仕掛けもチヌ釣りと余り変わらず、生きエビの代わりに青ゴカイを使用してもよい。
仕掛け タナ 湾内約1.50㍍ 青戸入り江約70㌢
大物ばかりが釣りでなく、夜の市が始まる頃から、小アジ釣りのシーズンとなり家族連れで楽しめる。アミエビのレンガを買ってサビキ釣り、アミサシでウキ釣りも楽しいもの。夜釣りはライトを照らして、少し海面の薄暗い所を狙えば良い.夜釣りは蚊が多いので、『虫避けスプレー』を忘れずに.釣り終われば撒き餌の入っていた袋ゴミは持って帰りたいものだ。前島埠頭などシーズン中など見られたものではない。
秋
『天高く馬こゆる秋』人も、魚も食欲の季節となり、魚は長い越冬生活に入る前の体力づくりに懸命になり食いが起ち、思わぬ多釣りができるのもこの時期である。春の稚魚もこの頃には、大きく育ち鉛筆ぐらいのサヨリも25~30㎝位に、春に10㎝位のチヌやグレが20~30㎝位まで育ってくる。又、潮適しの良い所ではサンバソウ(縞鯛)、カワハギなどが良く集まり誰にでも良く釣れるのはこの時期である。五目釣りには最高の季節である。朝夕外海に面した、防波堤で生きアジ、餌木(ルアー)でアオリイカが釣れるのもこの時期で、味は白イカにも負けぬものである。又、湾内では餌木でタコ釣りの要領でゆっくり底を引くと紋甲イカが誰にでも良く釣れる。両方共釣り時期は9~12月頃
冬
水温もこの時期になると、少しずつ下がり釣り人も少なくなり、釣れる魚も非常に少なく限られてくる。水温が下がればサヨリが防波堤付近まで近より、岩場の海草等に卵を産みにくる。又、チヌはこの時期から春先にかけて、大物が釣れる。稚魚は防波堤で育ち外海へ、荒磯の王者と言われる石鯛も稚魚の内は防波堤で、グレ・チヌ・ソイ(メバルに似ている)もその仲間であり、そのまま防波堤付近に居いてしまう魚もいます。釣り人は総てと言って良いほど天狗であり、ビギナーの師匠である。その釣り場の仕掛けが、わからなければ教えを乞うと、わりに丁寧に教えてくれる(中には知らん顔をする人もいるかも?)
注意 刺されたら痛い
アイゴ 尾鰭が深く切込んでいるのが特徴である。背鰭、胸鰭に鋭い 毒針を持っている。
ハオコゼ 湾内の岩場藻場に住み着き背鰭に鋭い毒針を持ったガンラに似 た魚である。
ゴンズイ 夜釣りをしていると、ナマズに似た縞模様の魚が釣れることが ある。胸鰭と背鰭の所第一棘に鋭い毒線を持つ。
これらの魚に刺されれば釣りどころではないから、注意すること 身近な磯、防波堤釣りの四季を追って行くと、楽しい釣りが出来ます。 1997年7月18日記